図録(PDF、33MB)
目録(PDF、800KB)
作品単体写真(ZIP、300MB)
横浜赤レンガ倉庫イベントページ
Ten・ten 2019 in 横浜赤レンガ倉庫 ‐両極の書‐
現代書の最先端を走る漢字・仮名23名、前衛23名、計46名の作家による連立個展です。文字のある書、ない書、紙墨筆を使う書、使わない書。ここは前代未聞にして百花繚乱の世界です。はぁ? へぇ! ほぅ! むむ、ふふふ、と理屈抜きにたのしめます。
主旨
戦後、書のルネッサンスといわれた隆盛期(1945〜1970)から半世紀を経た今、書の世界は低迷の底にいる。そこから脱する熱気が生まれる気配もない。
1955年 前衛書が日展脱退後、いわゆる伝統書と前衛書が席を並べたことはなかった。その後、漢字・仮名と前衛書は何処を目指し、どう育ってきたかを改めて検証し、世に問うてみたいと思う。
両サイドの最先端の作品を並陳することで見えてくるものは大きい。
前代未聞のこの場が「未来の現代書」への熱い入口となることを願いつつ この企画を実施する。
―
漢字・仮名・前衛に特化した理由は、本展のねらいをより鮮明にする為です。もともと書は漢字と仮名からできています。
漢字と仮名の人々は、書の美をより深く掘り進め、そこから湧き出る 清浄な水をくみあげる縦軸の仕事かもしれません。前衛は、書の可能性を求め、砂漠や月に出かけて美味しい水をさがし、くみあげ、生きる世界を広げる横軸の仕事かもしれません。
この縦軸と横軸を組み合わせて新しい泉をつくってみようか、というたくらみです。
その為には、展覧会は、シンプルな方が、わかりやすいということです。
―
少子高齢化、文字離れ、IT時代と言ってみたとて、何も始まらない。似たり寄ったりの作品(もの)ばかりでマンネリ状態の公募展にはたよれない。社中展やグループ仲良し展を見にくる人は身内だけじゃ やる意味ない。広がりもない。驚きもない。全く井の中の蛙じゃあないか。さみしい限りだ。
書に未来はあるのか? いっそ戦後書の両極端を並べてみれば、その振幅や色相いや匂いが少しは見えてくるんじゃないか。重なる部分もあるかも知れない。筆持つ作業でつながることもあるかもしれない。キャリアやしがらみを超えたところでの共演は響演になるかもしれない。そこから何か ほんの少しでも未来が見えてきたら、これはまさに事件じゃないか。歴史にのこる半世紀ぶりの大事件じゃあないか。
出品者
漢字・仮名:赤平泰処、生駒蘭嵩、石坂雅彦、岩井秀樹、上籠鈍牛、植松龍祥、江草幽研、大林靖芳、越智麗川、尾西正成、川西美智、齊藤紫香、棧敷東煌、杉山曉雲、鈴木汪慶、種家杉晃、原雲涯、藤波艸心、幕田魁心、松尾光晴、水川芳竹、森廣青寿、吉澤大淳
前衛:安藤一鬼、石井抱旦、草津祐介、佐伯孝子、坂巻裕一、榛葉壽鶴、杉山勇人、高橋彰子、竹澤順子、竹下青蘭、竹原慎一、竹村美園、谷川ゆかり、中西浩暘、東素子、日野公彦、平蔵、堀内肇、宮村弦、森紅汀、八重柏冬雷、山下恭代、山本尚志
2019年6月3日 月曜日〜6月9日 日曜日
11時〜18時(初日は13時〜、最終日は〜17時)
横浜赤レンガ倉庫 1号館 2階
入場無料
シンポジウム:6月8日 土曜日 15〜16時(ゲスト:笠嶋忠幸氏(出光美術館学芸課長))
ワークショップ:毎日 13時〜
ギャラリートーク:毎日 14時〜
「書作の根底を見直す」菅原教夫(読売新聞編集委員、美術評論家)
この展覧会では、参加作家たちが自らの書作の根底を見直そうとしているように思われる。伝統書と前衛書を隣り合うように並べて刺激し合うとか、一人当たりの展示スペースが広いといった開催理由は外的なもので、作家たちのなかから本展構想がわき出てきた背景には、いまの時点で書作することの意味を確かめたいとの内的な欲求があると想像する。
伝統書の作家たちの顔ぶれを見ると、すでに日展で二回の特選を得て書家としての立場を築いた人や、それに近い力量の持ち主がそろった。しかし、彼らはその立場に安住するのでなく、好きな書を十分に生ききるにはどうすればいいのかと、その手掛かりを求めているように見える。
たとえば本展の構想にかかわった一人、石坂雅彦の場合は金文による作品で二度の日展特選を受賞したが、その後はあえて金文を離れ、時代の下った石刻などの古代文字の探求に入った。侯馬盟書にしばらく取り組んだのに続き、このところトウ(登偏におおざと)石如の篆書の所以たる祀三公山碑に打ち込んでいるのがそれである。ここからは篆書書法の根底をつかむためにその悠久の歴史に分け入りたいとの思いが伝わってくる。あるいは関西から意欲的に参加した尾西正成は王羲之をベースに墨蹟を加味した行草で知られる書き手だが、近年は書線を激しく躍動させる表現主義の度合いを強めている。この振り子はいったんとことんまで振りきってみなければなるまい。でなければ古典に備わる抑制の美学の本当のところも血肉化できないであろうから。
このような個々の作家の真摯な試行は実にうれしいものである。青山杉雨と現代作家の営みを話し合っていたころ、抜群の批評眼の持ち主であった巨匠はよくこういう言い方で他人の作品を評した。「菅原君、しかしああいう作品をかいていて本人は満足できるものだろうか」。今日、何とも挨拶に困る作品に出合うたび、僕の頭のなかでこの言葉がよみがえる。もちろん作品を認めていないことの遠回しな言い方で、もしそうした作品に本人が満足しているのなら何をかいわんやというわけだ。
本展の作家たちは自分の書作はこれで満足かという根底的な問いを自分に突き付けているように映る。書作に向かう姿勢、そして今日の書のあり方を検証しながら、一層豊かな自分の書を確立したいからである。
「引っ掻き回そう!」桐山正寿(毎日新聞学芸部)
自らの日常生活を考えてみる。職業は会社員、職種は新聞記者。「書く」ことで収入を得ているはずなのに、書いてはいない。パソコンのキーボードを叩いている。
書の担当となった時に、お目にかかる方々から、美しい文字が綴られた手紙をいただいても、楷書以外は読めない、と怯えた。ところが、支障はほとんどなかった。肉筆の手紙をいただくことは、滅多になかったからだ。
現代は、人間が手を動かして書いた文字は生活から完全に切り離されてしまった。ここに、書の危機も可能性も、潜んでいるように思われる。
「芸術作品を創造しているんだ」と叱声が飛んできそうだ。しかし書人は作品を売って暮らしているか? 書を教えて食べているのではないか。街角に掲げられた看板や刻された標識に思わず立ち止まらせてしまうような書を見つけられるか? 百歩譲って書展会場に身内以外の人が、どれだけいるだろう。
「両極の書」が「書って何だろう?」、と思い巡らす契機となってほしい。書人仲間、そして芸術を必要とする人々の間で。今回展のカタログは「漢字・仮名」と「前衛」が、逆立ちするように編集されている。企画者の強い意欲と機知が感じられる。開催主旨には「身内だけじゃ やる意味ない。広がりもない。驚きもない。全く井の中の蛙じゃないか。さみしい限りだ」とあった。尻馬に乗って付け加えよう。書の楽しさは、まだまだ世の中に知られてはいない。口コミ(インターネットもいいだろう)で直接、周りの友人に伝えようではないか。
喧々諤々、書について語り合おう。現代の書が「低迷の底」(主旨文)にあるのなら、なおさらだ。赤レンガ倉庫という会場は開かれた広場となり得る。進取の気性を秘めた会場なら、少々乱暴な物言いも許されるのかもしれない。「低迷の底」を引っ掻き回そう! 「書く」=「掻く」と承知している。言葉の原義にも、つながっていくに違いない。
主催:Ten・tenプロジェクト
後援:毎日新聞社、神奈川新聞社
代表:石坂雅彦、石井抱旦、生駒蘭嵩(相談役)
事務局・問い合わせ:0467-86-2615(石井抱旦)
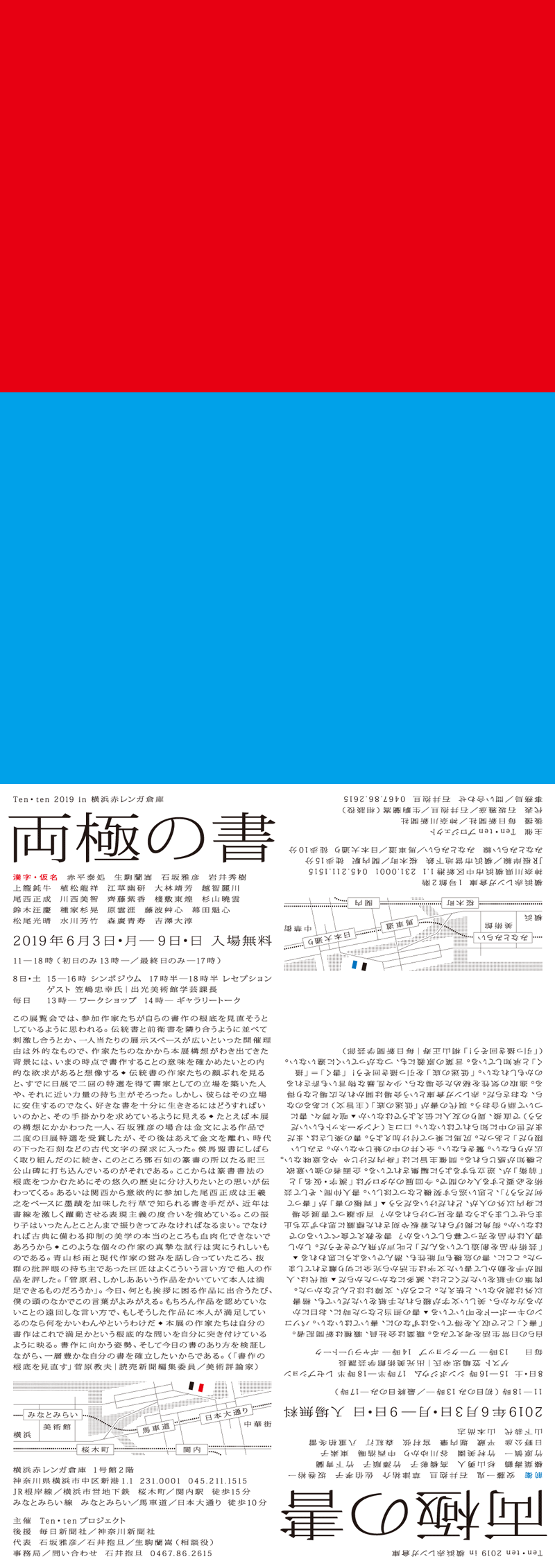
要項(出品者用)




